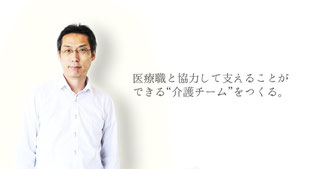倶楽部Canvas collaboration entry-instructor
上野邦靖(Ueno Kuniyasu)
介護技術担当の上野邦靖です。よろしくお願い致します。
世の中様々な介助方法がありますし、それぞれ素晴らしい取り組みをされていると思います。私の意見もそのうちの一つとして見て頂ければ結構です。要は、利用者が楽で辛くなく、介助者も無理のない介助の考え方はどのようなことだろうか?なるべく、誰にでもできるような方法をご紹介出来ればいいと考えています。
勤務先:オレンジホームケアクリニック



こんなことを考えています!!
改めてマネジメントについて考えてみたいと思い、ドラッカーの「マネジメント」
を読み返してみました。
ドラッカーはこう言っています。
『企業や法人の目的は「顧客の創造」である』
もうすこし福祉業界に引き寄せて
考えてみました。
「顧客の創造」とは何か?
目に見えていなければ「顧客」はいない。
目に見えない?
ニーズが見えていない?
本来「顧客」でありえる人が
「顧客」として見えない。
これは私たちの「顧客」ではない、と見過ごしていないか?
それは私たちの能力がないから?
技術が磨かれていないから?
いや、それ以前の問題があるのではないか。
ニーズの捉え方ができていないのではないか?
そのためには何が必要か?
もしかしたら「教養」の視点が欠けているかもしれない。
職業人として、と言うより「人」として生きる上での心構えのようなもの。
それが必要なのではないか?
その上で職業としての「目的」は何だろう。
例えば介護福祉士の職業とは何か?
職:生活の直接支援職
業:命を預かるサービス業
この職業観を見るに付け、幅広い知識と深い専門技術が必要なことが見えてきます。
だからこそ、「教養」の捉え方が大切になってきます。
脳科学者の茂木健一郎氏は「教養は生きる上での道しるべ」だと次のように言っています。
『「教養」とは、一生をかけて必死になって醸成していくべきものである。
何が起こるかわからない人生において、生きる上での道しるべをあたえてくれるものである。
それは、万人にとって必要なもの。決して、机に座って本を読むことによってのみ身につくものではない。
私たちが生きる上で時々刻々経験すること。その細やかなひだの中から、次第に醸成されてやがて血肉になるのが教養である。
~教養を身につけるということは、すなわち、自分がどれくらいものを知らないかということを自覚しているということである。それでいて、決して投げやりにはならないということである。未知なものに対して、積極的に、かつ真摯に向き合う。そのような態度を身につけていることが、教養、すなわちコモンセンスなのである。』
(林望、茂木健一郎共著 『教養脳を磨く』より)
こうして見ると、「教養」とは「生き方」になってくるのかもしれません。日頃、介護職には「知識と技術」が必要だと、そう言っていますが、それはあくまでも「手段」としての「知識と技術」選択肢を広げるためのもの。介護職としての「目的」がまずなければならない。
「生き方」としての「教養」と「手段」として「知識と技術」。そこには「利用者視点」が不可欠です。それを踏まえて、先に挙げた職業観を考えてもらいたいです。
今日はこれまで。